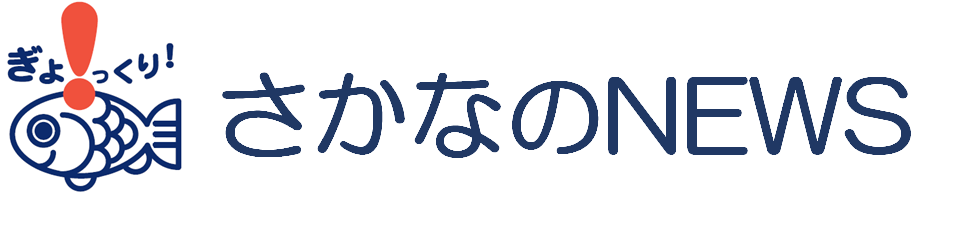「魚離れ」が話題になって久しいなか、「魚を食べましょう」とストレートに呼びかける取り組みをよく見かけます。しかし、それは本当に効果的なアプローチなのでしょうか?
たとえば車やお酒の消費が減ったとき、「車を買おう!」「お酒を飲もう!」と呼びかけるのではなく、ライフスタイルに寄り添った提案や新しい楽しみ方の開発が行われます。魚にも同じ発想が必要です。
魚を食べたくなる仕掛けを考えること。これこそが、魚食文化の未来をつくる第一歩ではないでしょうか。
実は「魚を食べたい人」は、すでにたくさんいる

一般社団法人大日本水産会が2019年に行った消費者の意識調査では、
- 魚料理が「好き」又は「やや好き」と回答した人は約9割
- 魚を食べる量や頻度を増やしたいと回答した人は6割以上
となっていました。
(参考:水産庁HP(2)水産物消費の状況)
それ以外の多くの意識調査でも、「魚をもっと食べたい」と答える人が8割近くにものぼります。
ではなぜ食卓に魚が並ばないのでしょうか?
理由はシンプル。
「手に入れにくい」「扱いにくい」「調理のハードルが高い」など、消費者の生活にフィットしていないのです。
たとえば、漁師の現場では「アジ2キロ」「サバ4キロ」などの単位で魚が届けられることがあります。
これでは都市部の一般家庭では持て余してしまいます。
魚を家庭で扱いやすく、生活に馴染む形に変える工夫が必要なのです。
本当に必要なのは「魚食普及」よりもマーケティングの視点
魚業界では、多くの場面で「魚を食べましょう」「もっと魚を食べてください」といった呼びかけが繰り返されています。しかし、それだけで人の行動が変わるわけではありません。
では、どうすれば魚を食べたくなるのか?
答えは、マーケティングの視点にあります。
誰に、どんなシーンで、どんな方法で届ければ、魚を自然に選びたくなるのか。
その問いを持つ必要があります。
- 魚を食べていない人は、どんな生活をしているのか?
- 何が「めんどう」「ハードルが高い」と感じられているのか?
- 逆に、どんなときなら魚を食べたくなるのか?
- どんな伝え方、見せ方なら「おいしそう」「かっこいい」と思ってもらえるのか?
そういった問いを深掘りすることが、魚食を広げる第一歩になります。
とはいえ、魚を届ける漁師や生産者にとって、都会の暮らしを直接体験することは簡単ではありません。
自然を相手にする仕事だからこそ、時間も環境も限られているのが現実です。
でも、今は産直ECやSNSなどを通じて、消費者の声を直接知ることができます。
実際に足を運べなくても、「都会ではどんな魚が求められているのか」「どんな食べ方が喜ばれているのか」を知る方法はたくさんあります。
届ける側が相手を知ろうとする努力。これもまた、マーケティングの大切な一歩です。
「魚好き」だけに届けても広がらない
魚イベントや試食会に来るのは、もともと魚が好きな人たちです。
そこで盛り上がるのはもちろん大事なことですが、それだけでは「ふだん魚をあまり食べない層」には届きません。
届けていきたいのは、魚にあまり興味がない人や、普段はあまり食べる機会がない人たちです。
そんな人たちが「ちょっと食べてみようかな」と思えるようなきっかけを、もっと増やしていく必要があります。
たとえば、音楽フェスやスポーツイベント、日常のスーパーやコンビニ、SNS上のトレンドの中に、さりげなく魚の魅力を差し込んでいく。
そうした柔軟な発想が、これからの魚食文化を育てる土台になっていきます。
魚をもっと食べてもらうために、できること
魚をもっと食べてもらうために、どんなことができるのでしょう。
たとえば、こんなことが考えられます。
- 下処理や味付けが済んだ、すぐに使える形で売る
- おしゃれで手に取りたくなるパッケージにする
- 「忙しい朝にぴったり」など、食べるシーンを具体的に提案する
- スーパーやイベント以外の、思いがけない場面で魚と出会わせる
これからの魚食文化を育てていくには、「食べて」と押しつけるのではなく、工夫を凝らして「届け方」を変えていくことが大切です。
消費者に近づく努力を重ねながら、魚の魅力が多くの人に届く日を目指して。
私たち自身も、届ける側としてのあり方を問い直していきたいものです。