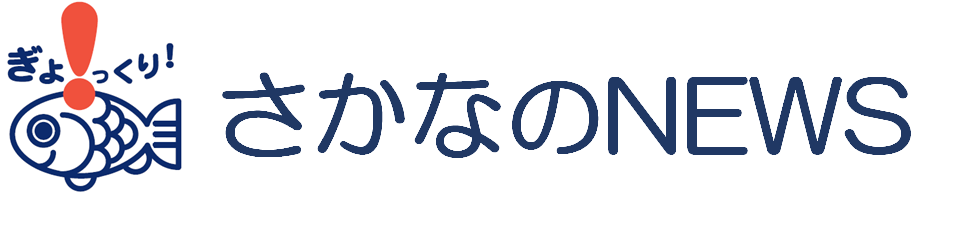さかなのNEWS編集長のながさき一生です。
今日は「水産業界のブランド化」についてご紹介します。
私はこれまで全国の漁業者や養殖事業者、漁協の方々とお仕事をしてきました。
そのなかで、水産品の「ブランド化」に関するご相談を受けることもしばしばあります。
ブランド化の専門家として、現場でよく見かける「陥りがちな落とし穴」を5つに整理してご紹介します。
1. 名前をつけて満足していないか?
「ブランド化=名前をつけてタグを付けること」と勘違いされているケースが非常に多く見受けられます。
けれど、これはあくまで“入り口”にすぎません。
本質的なブランド化とは、市場分析と戦略設計の上で「どんなターゲットに、どのような価値を提供するのか」を明確にすること。そしてその価値を一貫して伝え続けることです。
「うちの魚は良いから売れるはず」と願望だけで名前をつけて終わっていませんか?
2. ブランドの価値が曖昧になっていないか?
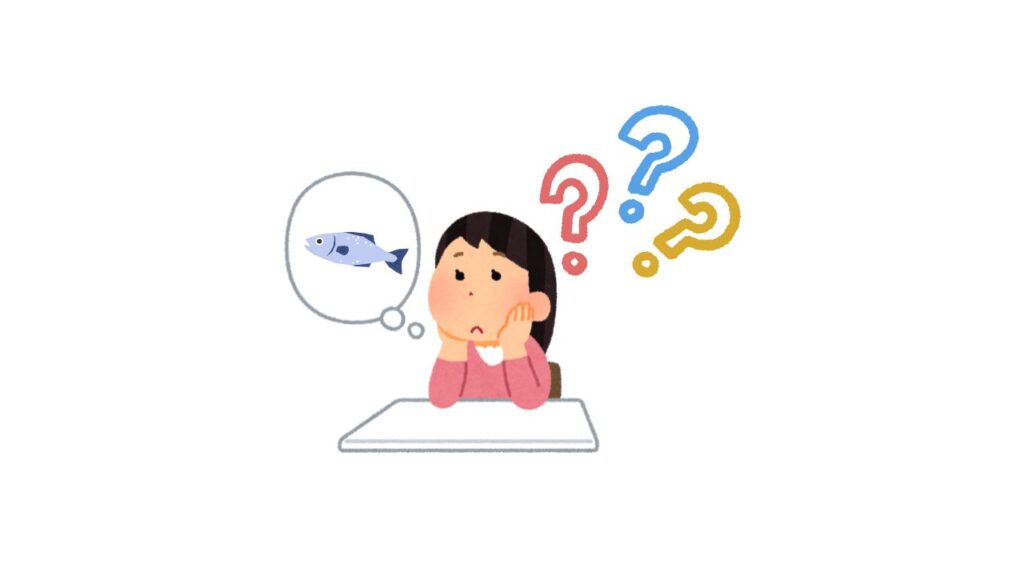
多くのケースで「美味しい」「品質がいい」といった抽象的な表現で価値を語ってしまいがちです。
しかし、水産品が持つ価値にはさまざまな種類があります。
- 鮮度の良さ
- 脂のノリ
- 日持ちの良さ
- 調理のしやすさ
- サステナビリティ(環境配慮)
自社の商品がどの要素に強みを持つのかを見極め、「誰にとって、どんな価値があるのか?」を明確にする必要があります。
3. ネーミングが伝わりにくくなっていないか?
ネーミングもブランド戦略の大切な要素です。
「それ、何の魚?」と聞き返されるような名称では、消費者の記憶には残りません。
SNS時代の今、情報に接する時間はほんの数秒です。
名前を見た瞬間に「どんな商品で、どんな価値があるのか」が伝わる必要があります。
できれば3〜4文字くらいの短いものや、音の響きでどのような商品か伝わるようなシンプルさが理想です。
4. 生産者や関係者の合意形成を忘れていないか?

特に漁協や複数の漁業者が関わるブランドづくりでは、「顧客目線」だけでなく「参加者の納得感」も重要です。
例えば、
- ブランド名の決定時に、誰か一人が推し進めた名前ではなく、参加者全員が「これなら自分たちの誇りになる」と感じられるか?
- 誰がどのような条件でブランドを使えるのか、品質基準やルールは公平に設定されているか?
- 会議の場で意見を出しづらいメンバーがいないか、合意形成のプロセスが透明で開かれているか?
といった点が、後々のブランド維持に大きく関わってきます。
特に一次産業では、ブランディングは「外への発信」であると同時に、「内側をまとめるための旗印」にもなります。
5. ブランドの品質管理ができているか?
ブランドは「一定の品質が約束されている」からこそ信頼されます。
たとえば、大手の飲料ブランド「コカ・コーラ」が店舗や時期によって味が違っていたら、人は安心して買い続けることができません。
それと同じように、魚のブランドも「この名前がついていれば、○○という品質だよね」と認識されてこそ、ブランドとして機能します。
しかし魚は非常にデリケートな商材です。
水揚げ後の扱いや温度管理ひとつで、品質は簡単に変わってしまいます。
例えば、関サバのようなブランド魚でも、途中の流通で常温放置されれば品質は大きく劣化します。
ブランドが最終消費者に届くまでの「流通設計」は重要な視点です。
中間業者や販売先の管理体制が整っていないと、せっかくのブランド価値が途中で損なわれてしまうリスクがあります。
- 中間業者への品質管理の共有と協力体制の構築
- 直販を行う場合は、自社で最終品質まで責任を持つ体制
- クレーム対応やフィードバック回収のフロー整備
など、「売ったら終わり」ではない体制づくりが、信頼の積み重ねにつながります。
おわりに
水産業のブランド化は、名前をつけることでも、タグをつけることでもありません。
誰に、どんな価値を、どうやって届けていくのか。そして、その品質をどう守っていくのか。
ブランドとは、目に見えない「信頼の仕組み」なのです。
水産業に関わる皆さんが、それぞれの地域や魚に誇りを持ち、価値を最大限に届けていけるように。
この情報が少しでもお役に立てば幸いです。
「うちの魚にもブランドの力を取り入れたいけど、どこから始めればいいか分からない」
「名前はつけたけど、その先の設計がうまくいかない」
そんなお悩みがあれば、ぜひ一度ご相談ください。現場目線と戦略目線、両方からサポートさせていただきます。
「情報発信したいけど、パソコンは苦手…」
「時間も手間もかけられないけど、ちゃんとしたホームページがほしい」
そんな声にお応えして、水産業者のウェブ担当として企画から制作・更新までをまるっとサポートする、水産業のためのホームページ制作サービスです。