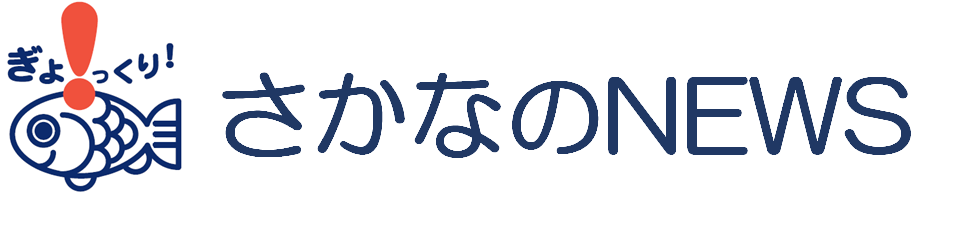さかなのNEWS編集長のながさき一生(@nagasaki_ikki)です。
最近は不思議なことに、林業の方からセミナーや取材などで声をかけてもらうことが増えてきました。食と魚の専門家として活動してきた身としては、少し意外な展開です。
林業と漁業。
一見まったく別の産業に見えますが、話を聞けば聞くほど「同じ課題を抱えている」と感じます。
この記事では、林業と漁業の共通点から、これからの資源との付き合い方について考えてみたいと思います。
林業の現場から見えること

林業は、長い時間をかけて成り立つ仕事です。
木を植えてから伐採して売るまでには、数十年かかります。祖父が植えた木を、息子が育て、孫がようやく伐る。そんな流れが当たり前です。
収益が出るのは、木を売るときだけです。
けれど、それまでには草刈りや間伐、水の管理など、多くの作業があります。どれも山を健康に保つために欠かせませんが、すぐにお金になるわけではありません。
こうした山の手入れは、海にも影響します。
山の栄養は川を通って海に届きます。森が荒れれば、海の環境にも影響が出るのです。
漁業と林業の共通点
林業と漁業は、場所は違っても、自然を守るという点では同じです。
たとえば、藻場を守ったり、稚魚の育つ環境を整えたりといった作業。これらはすぐに収入にはなりませんが、魚を育てるうえでとても大切です。
また、どちらの業界にも認証制度があります。
林業にはFSC、漁業にはMSCなどがあります。どちらも環境に配慮した取り組みを示すものですが、取得には数十万円〜数百万円といったお金がかかります。
そのため、小さな事業者にとっては負担が大きく、取りたくても取れないケースもあります。
制度自体は良くても、「認証がない=環境に悪い」という誤解につながってしまうこともあるのではないでしょうか。
自然との関係を見直すきっかけに
今の社会では、「アジが食べたい」「この木材だけ使いたい」といった、人の希望を優先して自然を動かそうとすることがよくあります。
でも、自然は人の思い通りにはいきません。魚にも旬があり、木にも育つペースがあります。
特定の魚だけをとり続ければ、海のバランスは崩れます。一本の種類の木ばかりを植えれば、森は弱くなります。
昔の日本には、自然に合わせて暮らす知恵がありました。
その季節にとれる魚を食べ、山では多様な木を育て、必要に応じて使っていました。
そうした暮らしは、自然に無理をさせず、長く資源を使い続けるための工夫でもあったのです。
林業も漁業も、本来は「自然に合わせること」で成り立つ仕事です。
早く育つ木や、よく売れる魚だけに頼るのではなく、自然の流れに目を向けること。そこに、これからの持続可能な道があると感じています。
魚や食に関するコンテンツ制作、執筆、コンサルティング、講演などのご依頼も承っています。
ご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。