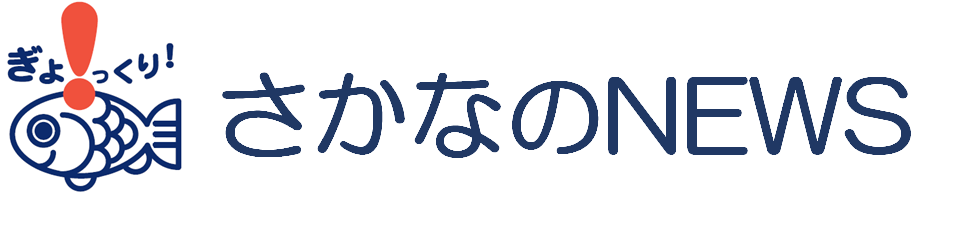スーパーに並ぶ「国産カツオ」の文字。
なんとなく「日本の漁師さんが釣った魚」だと思っていませんか?
たしかに、カツオは日本近海で水揚げされているれっきとした国産魚。
でも実は、その漁を支えているのは、日本人だけではありません。
カツオの一本釣り漁船。その現場の中心にいるのは、インドネシアから来た船員たち。
いま、日本の漁業は「多国籍チーム」で成り立っているのです。
漁船の7〜8割が外国人クルー?
「船長さんは日本人。でも、実際にカツオを釣っているのはインドネシアの方という船は結構ありますよ」
そんな声が、漁業関係者のあいだでは珍しくなくなってきました。
一見すると「国産のカツオ」。しかし、その漁の担い手を見てみると、実は外国人が中心となっている現場が数多く存在します。
その背景にあるのは、漁業の人手不足と高齢化。
沿岸・沖合・遠洋問わず、日本の漁業は長年にわたって後継者難に直面してきました。若者の漁業離れが進む中、人材確保は年々厳しさを増しています。
そこで注目されたのが、海外からの人材。
なかでもインドネシアとの関係は深く、1980年代から国同士で人材協定を結び、漁業技術と人材の交流を行ってきました。
この仕組みによって、現在では多くのインドネシア人が日本の漁船に乗り込み、カツオやマグロの一本釣りに携わっています。
実際、乗組員の7〜8割をインドネシア人が占める漁船も珍しくありません。
彼らが国産と呼ばれる魚の、その現場を支えているのです。
共に働く。そのための“土台づくり”を

多国籍化が進む一方で、制度や現場の受け入れ体制はまだまだ追いついていません。
高額な仲介手数料、情報格差、企業とのミスマッチなど。
こうした「目に見えないトラブル」が、外国人と日本企業のあいだに壁を生んでしまうこともあります。
本来なら、国や文化を超えて共に働けるはずの現場が、うまく機能していないケースも少なくありません。
だからこそ、受け入れる側、送り出す側、そして働く人。
この三者がちゃんと理解し合い、誠実につながる仕組みを作らなければいけません。
「魚を釣る人」にも目を向けてみよう
魚のことを考えるとき、つい私たちは商品としての魚ばかりに目を向けがちです。
でもその背景には、海に出て、釣り竿を握り、汗を流す「誰か」の存在があります。
そしていま、その誰かは日本人だけではなくなっています。
「国産」カツオの一本釣り。
その釣り竿を握っている、遠くインドネシアから来た若者の姿があります。
漁業の多国籍化は、これからの日本の魚ビジネスを考えるうえでの大切なヒントになるはずです。