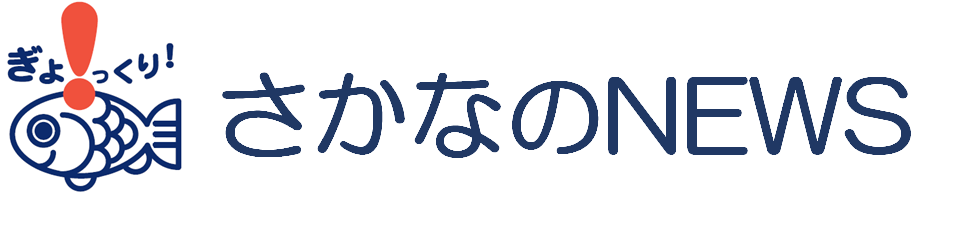魚の細胞を増やして食べられる魚肉を作る、細胞水産業。
水産資源を守るため、世界中で研究が続けられている分野です。
そんな細胞水産業の最前線を、イスラエルの培養肉スタートアップ企業Forsea Foods(フォーシーフーズ)で日本でのビジネス部門のマネージャーを務める杉崎さんに話を伺いました。
世界が注目する培養水産業
Forsea Foodsが2024年1月に発表したのは、培養生産したうなぎで作られた、蒲焼きや握り寿司といった日本料理の数々。

そう、ただのうなぎではありません。
培養生産したうなぎです。
培養生産とは一体なんぞや、と疑問を持たれた方も多いかと思われます。
培養魚肉とは、魚の「味わいたい部位の細胞」を人工的に増やして作られた、食べられる魚肉のことです。
世界的にはブリやサーモンといった魚の培養肉を試作品を作っているベンチャー企業もあります。
天然でも養殖でもない培養水産業。
このような新しい流れの理由としては、将来的な水産資源への不足が挙げられます。
私たちが魚を食べ続けるための選択肢のひとつとして、研究が進められているのです。
うなぎ培養肉、開発の理由

フォーシーフーズでは数ある魚のうち、うなぎの開発を進めています。
蒲焼きなどで人気のうなぎですが、稚魚であるシラスウナギの漁獲量が減ってきているのは有名な話です。
また、日本以外でもうなぎを食べる国は多く、アジア圏を中心に世界中で食べられています。
ニーズはあるのに稚魚が獲れない。
さらに細胞培養で代替製品を作れるという技術的な面でもクリアしていたことから、うなぎの培養魚肉の開発を進めているとのことです。
私たちがうなぎ培養肉を食べられるのはいつ頃?
試作段階のうなぎ培養肉ですが、フォーシーフーズでは2025年中の製品化を目指して開発を進めています。
フォーシーズ以外にも細胞水産業の企業はあり、研究が進められているので、ひょっとしたらもっと早く商品化が実現するかもしれません。
ただ、日本では法整備がまだ整っていないこともあり、安全性の基準など検討している段階とのこと。
海外に目を向ければ、シンガポール、アメリカ、イスラエルといった国ではルールが整っていて販売も可能になっています。
養殖と細胞水産業、それぞれの良さで広がる選択肢
培養水産業は特定の部位の細胞を増やすことで、食べたい部位の魚肉を作り出すことができる技術です。そのため、フードロスや魚の絶滅危惧といった課題を解決する可能性を秘めています。
一方で養殖のうなぎにも細胞水産業では出せない魅力があります。
うなぎを1匹丸々作り出すことは細胞水産業ではできないことなので、骨や出汁といった、様々な部位の味が混ざり合う複雑な味わいは養殖のうなぎならでは。
うなぎ以外でも、例えばあら汁は細胞水産業では出せない味です。
「今食べている魚が50年後も食べられる世界でありたい」と語った杉崎さん。
どちらが良いということではなく、それぞれの良さを生かして、私たちが魚を食べ続けられる未来を作っていきたいですね。