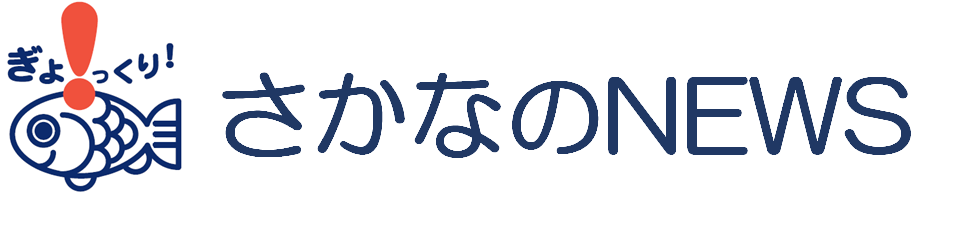秋の味覚といえば、やっぱり「さんま」。
今年はスーパーでもよく見かけるようになり、食卓を賑わせてくれています。
とはいえ、店頭に並んださんまの中から「美味しい1尾」を選ぶのは難しいもの。
今回は美味しいさんまの見分け方をご紹介します。
1. 体型を見る 〜小顔のさんまが美味しい〜
魚を選ぶときにまず注目したいのが「顔と体のバランス」です。
これはさんまに限らず、栄養をしっかり蓄えて大きく育った魚ほど「小顔」に見える傾向にあります。
具体的には、頭から背中にかけてのラインをチェックしてみましょう。頭の付け根から背中がふくらみ、ポコッと盛り上がっているものは、胴体に厚みがあり、脂がのっているサインです。逆に、頭から背中がすっと一直線につながっている個体は、まだ細身で栄養が十分ではない可能性があります。
買い物のときは、何匹かを並べて比べると違いがはっきり分かります。小顔に見えるさんまは身に力があり、焼いてもジューシーで、口に入れたときの脂の甘みが格別です。見慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、コツをつかめば「あ、この1尾は当たりだな」と直感できるようになります。
2. 口先の色 〜黄色は栄養たっぷりのサイン?〜

さんまを選ぶときに、意外と見落とされがちなのが「口先の色」です。
諸説ありますが、一般的に、口先がほんのり黄色く色づいているさんまは、餌をしっかり食べて栄養を蓄えているといわれています。市場や漁業関係者のあいだでも、「黄色い口先は美味しい印」として知られています。
ただし、科学的に完全に解明されたわけではなく、「必ずしも黄色だから美味しいとは限らない」という意見もあります。
とはいえ、店頭で複数のさんまを見比べると、確かに黄色い口先を持つものは体型もしっかりしているケースが多いのです。鮮度やサイズ、背中の盛り上がりなど他の要素と組み合わせてチェックすると、より「当たり」の1尾を見つけやすくなります。
ちょっとした豆知識として、選ぶ際の一つの目安として覚えておくと面白いですよ。
3. 鮮度を見分ける
魚の美味しさを大きく左右するのが「鮮度」です。
さんまの場合、まず目で見てわかるポイントがいくつかあります。
鮮度の良いものは、身がピンと張り、手に取るとしっかりとした弾力があります。また、背中の青とお腹の銀白色がくっきりと輝いているものは新鮮な証拠。逆に、全体的に色味がくすんでいたり、腹の銀色がぼやけていたりするものは時間が経っている可能性が高いです。
さらに、目の澄み具合も重要なチェックポイントです。透明感があり黒目がくっきりしているものは新しい証拠。時間が経つにつれて白く濁ってくるので、目の印象を確認すると鮮度が一目でわかります。
ただし注意したいのは、「鮮度」と「脂ののり」が必ずしも一致しないということです。鮮度が落ちて色が少し暗くなっていても、背中に盛り上がりがある個体は脂がしっかりのっている場合があります。一方で、見た目はピカピカで鮮度抜群でも、体が細く脂の少ない個体もあるのです。
つまり、さんまを選ぶときには「鮮度」と「脂ののり」を別物として考えるのがコツ。
焼き魚にして脂の甘みを楽しみたいなら、背中の盛り上がりを優先。
刺身や塩焼きでさっぱりした食感を味わいたいなら、鮮度の良さを重視するなど、料理の用途や好みに応じて選ぶと満足度がぐんと高まりますよ。
まとめ
今年のさんまは「当たり年」と言っていい状況。背中が盛り上がった小顔のさんまを選んで、旬の脂の美味しさを楽しんでみてください。
さんまは庶民の魚でありながら、その資源量や回遊ルートはまだまだ分かっていないことも多い魚です。だからこそ、旬の1尾を選んで味わう時間は特別なもの。今年の食卓にはぜひ「旬のさんま」を並べてみてください。