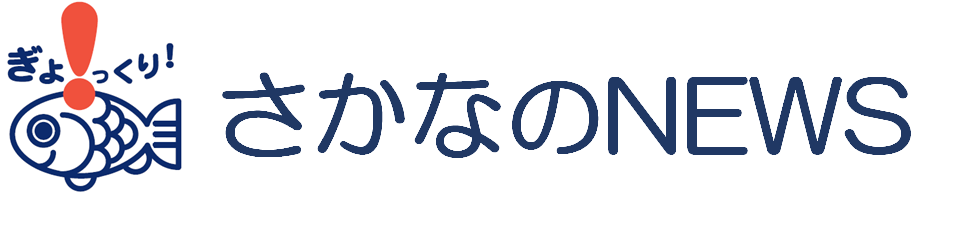魚は獲った後の処理、「締め方(しめかた)」によって、その後の鮮度や美味しさが大きく変わってきます。最近ではスーパーや通販で「神経締め」といった言葉を目にすることも増えてきました。ただ、普段水産業や釣りに馴染のない方にとっては、「それってどういうこと?」と思うことも多いはず。
この記事では、魚の締め方の基本から、近年のされることも増えてきた「神経締め」までを、わかりやすく紹介します。
魚を「締める」とは何か?

魚を釣ったり水揚げしたりすると、バタバタと暴れてしまいます。このままにしておくと、魚にストレスがかかって、鮮度が落ちたり、身が痛んだりしてしまいます。
この暴れを止めて、なるべくいい状態で保つために行うのが「締める」という処理。いわば、美味しさを守るためのスタート地点です。
締め方には色々な種類がある

■ 氷締め
魚を氷水に入れて冷やして動きを止める方法。たくさんの魚を一気に処理できるので、漁業などでよく使われます。
ただし、締まり方にムラが出ることもあり、魚によってはしっかり締まらない場合もあります。
■ 脳締め
魚の頭(脳)に衝撃を与えたり、ナイフで脳を破壊して締める方法。確実に魚を締めることができるので、鮮度をしっかり保ちたいときに使われます。
その分、1匹ずつ丁寧に扱う必要があり、手間がかかります。
魚の「血抜き」も重要!
締める行為と同時に「血抜き」を行うことがあります。魚の血は、臭みや腐敗の原因になります。だからこそ、早めに血を抜いておくことで、より美味しく、鮮度のいい状態を保てるのです。
血抜きをしっかりしておくと、透明感のある美しい身になり、保存期間も延びるというメリットがあります。
最近注目の「神経締め」って?
最近よく話題になるのが「神経締め」。これは、魚の神経を抜いてしまうという高度な処理方法です。
魚の背骨に沿って通っている神経を、針金を通したり、水や空気を使ったりして取り除きます。こうすることで、魚の体の細胞に「死んだ」という情報を伝えず、“生きている”状態をしばらく保てるのです。
また、これにより、死後硬直が抑えられて魚の身が硬くならず、うま味の元になる「ATP」という成分も多く残すことができます。その後、魚を寝かせる(しばらく置く)ことによって、うま味の多い美味しい魚になるというわけです。
ただし、神経締めの効果は、魚やシーンによってもマチマチです。また、死後硬直後に行っても意味がないので、注意が必要です。
中には、意図的に死後硬直後に神経を抜いて、価値の高い魚であると欺いている場合もあるので、信頼できる魚屋さんやブランドを選ぶのが安心です。
魚の締め方で、味が変わる
締め方ひとつで、その後の鮮度も、味も、保存のしやすさも変わってきます。最近ではこうした処理の違いを知ることで、より美味しくなる魚を選ぶ人も増えています。
スーパーで「神経締め」や「血抜き済み」と書かれた魚を見かけたら、ちょっと注目してみてください。
それは、より美味しい魚を届けようとする人たちの工夫の証かもしれません。