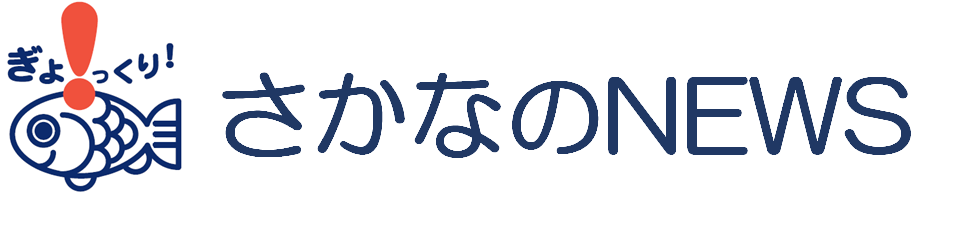土用の丑の日が近づくと、スーパーには香ばしく焼かれたウナギが並びます。その一方で、こんな声を耳にしたことはないでしょうか。
「ウナギって絶滅危惧種なんでしょう? 本当に食べてもいいのかな?」
たしかに、ウナギは数が減ってきていると言われています。でも、だからといって「食べないこと」がすぐに正解とは言い切れません。
この記事では、ウナギを取り巻く現状と、私たちができることについて考えてみたいと思います。
ウナギは本当に減っているのか?
現在、日本で流通しているウナギの99%以上が養殖によるものです。
とはいえ、その養殖には「シラスウナギ」と呼ばれる天然の稚魚が使われています。春先、川をのぼってくる小さなウナギの赤ちゃんを捕まえ、養殖池で1年以上かけて育てたものが、私たちの食卓に並んでいるのです。
ところが、シラスウナギの漁獲量は1980年代以降、極めて低く推移しています。東アジア全体では、ピーク時の1960年代には年間約3,600トンあった漁獲量が、2016年には約136トンまで落ち込んでいました。
参照:WWFジャパン
とはいえ、明るい兆しもあります。
2024年度に宮崎県で記録された漁獲量は、前年度の約191kgから約556kgと3倍近くに増加し、過去15年で最多となりました。
参考:朝日新聞
しかし、全国的には依然として低水準のままとなっています。
先の「ウナギは、絶滅危惧種」というのは、ウナギが国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストに指定されいることを指しています。例えば、ニホンウナギはレッドリスト上の「絶滅危惧IB類(IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの)」に指定されています。これは、科学的な知見による警告に留まるもので、具体的な規制は伴いません。
例えば、日本ではウナギを守るため、国際的な資源保護の合意に基づきシラスウナギの池入れ規制をしていますが、その上限は21.7トンとされています。ウナギを守るのは、「ウナギを食べ続けるため」「ウナギの食文化を守るため」です。そのためには、養殖、流通、加工等の技術を伝えていく必要もあります。そのためには、流通を止めるのではなく、適切に利用するということが大事なのです。
減少の理由はひとつではありません
ウナギが減っている理由は、決してひとつではありません。
- 海流や水温の変化など環境要因
- 河川整備による生息環境の変化
- 乱獲や密漁による資源圧迫
- 稚魚が海から川へ戻る際の生存率の低下
このように、自然環境の変化と人間の活動が複雑に絡み合い、ウナギの数が減ってきているのが現状です。
「食べるのをやめる」が正解なのか?
ある環境団体は、「土用の丑の日にウナギを食べるのをやめよう」と呼びかけていました。
ですが、それが本質的な解決につながるのかどうかは、少し立ち止まって考える必要があります。
というのも、今店頭に並んでいるウナギは、すでに1年以上前に捕獲され、育てられたものです。
私たちが今食べるのをやめたとしても、その命が海に返されるわけではありません。むしろ、消費されなかった分は行き場を失い、廃棄や食品ロスにつながってしまいます。
さらに、ウナギを食べる人がいなくなれば、ウナギを育てる人、さばく人、焼く人といった食文化を支える担い手たちも減っていくことになり、技術が継承されなくなります。そうなると、食文化は消失し、うなぎを食べ続けられなくなるのです。
食文化の担い手がいなくなるリスク
ウナギを守るというのは、単にその数を増やすことだけが目的ではありません。
「ウナギを食べる」という文化を、次の世代に受け継いでいくこともまた、守るべき価値のひとつだと考えます。
そのためには、養殖の技術も、職人の技も、流通の仕組みも維持していく必要があります。
つまり、「食べることが悪い」という考え方ではなく、「どう食べるか」が大切です。
私たちにできることは「選ぶこと」

私たちにできるのは、“どう食べるか”を意識すること。うなぎをめぐる問題は、「食べる or 食べない」の二元論ではないのです。
大量消費を促す訳ではありませんが、一人一人がウナギを大切に食べることが求められています。今ある資源を有効活用し、生産・流通を支える高い技術を応援するような「選択」が重要なのではないでしょうか。
「食べる」という選択の意味を見つめ直す
「ウナギは食べてもいいのか?」という問いに、「食べない」と答えるのは極端な反応です。
ウナギの命、育てた人の手間、焼き上げた職人の技。
その一尾の背後には、多くの時間と労力が積み重なっています。
私たちが目指すべきは、“うなぎを未来へつなぐ”ための選び方や関わり方を育てていくこと。
この夏、土用の丑の日にうなぎを手に取るとき、その一尾のうしろにある自然、技術、そして人の営みに、少しだけ思いを馳せてみませんか。